動画制作の流れを徹底解説【初心者向け】スムーズに進めるポイントとは?
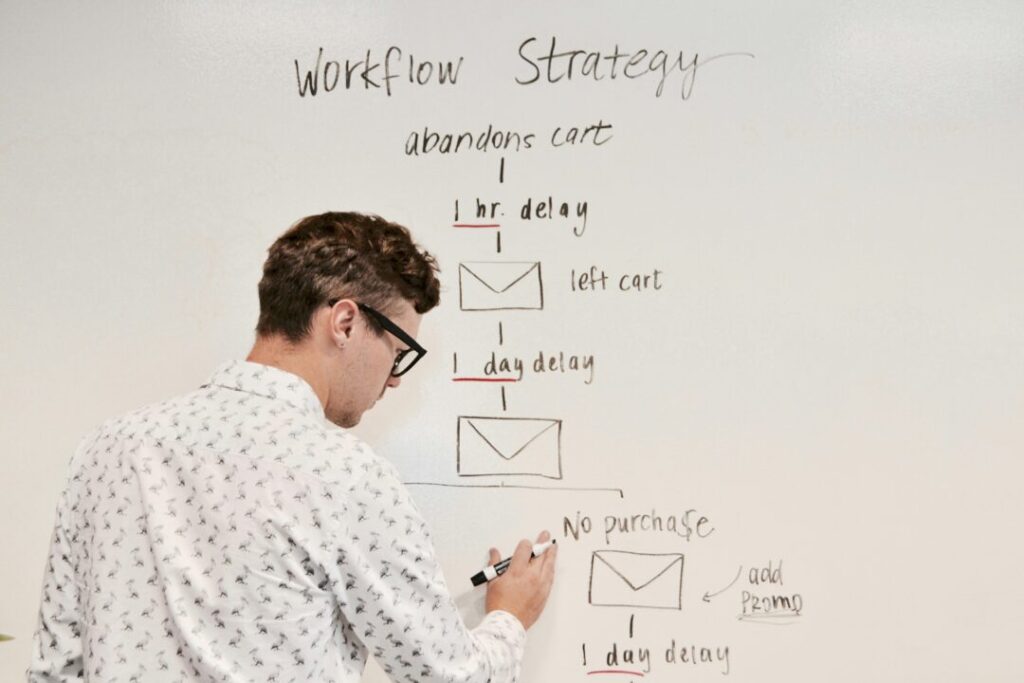
現代のマーケティングでは動画コンテンツが非常に重要になっています。事実、企業の91%がマーケティングに動画を活用しており、マーケターの88%が動画を戦略の重要要素と位置付けています 。また、動画を見た消費者の82%が製品やサービスの購入を決めたとのデータもあり、多くの人が企業からより多くの動画提供を望んでいます。こうした背景から、自社でも動画制作を検討する企業が増えています。
しかし、「動画制作の流れが分からない」「何から手を付ければいいのか不安」という初心者の方も多いでしょう。本記事では、企業のマーケティング担当者向けに動画制作の基本的な流れを解説し、制作を成功させるポイントを詳しく紹介します。動画制作をスムーズに進めるための事前準備や制作工程ごとの注意点、そして依頼先の選び方まで網羅しています。最後には、実績豊富な動画制作会社「サンキャク株式会社」の強みもご紹介します。ぜひ参考にしていただき、効果的な動画マーケティングにお役立てください。
動画制作の基本的な流れと制作スケジュールを解説【初心者向け】
まずは動画制作の一般的な流れを押さえておきましょう。動画制作の基本的な流れは、ズバリ以下のとおりです。
「依頼」→「企画(コンテ・シナリオ作成)」→「撮影」または「素材制作」→「編集」→「音入れ」→「納品」
制作会社への依頼から納品まで、このフローに沿ってプロジェクトが進行します。途中、制作会社から提案を受けてはフィードバックを返し、クオリティを高めながら完成へと近づけていくイメージです。なお、アニメーション動画の場合は上記フローの「撮影」が「イラスト作成(アニメーション制作)」に置き換わるだけで、基本的な手順は同じになります。
では、この一連の工程にどのくらい時間がかかるのでしょうか?一般的に動画制作の納期は約1〜3ヶ月程度を見ておくケースが多いです。企画内容や動画の尺によって変動しますが、例えば企画~構成に約3週間、撮影に1週間、編集に3週間程度というのが一つの目安です。実際には下記のような具体例があります。
- パワーポイントの簡易なスライド動画(約10分):約2週間
- サービス紹介動画(約1分):約2ヶ月
- テレビCM映像(約30秒):約3ヶ月
- eラーニング用研修動画(約30分):約3ヶ月
このように、動画の内容や尺が異なれば制作期間も大きく変わります。短い動画であれば数週間、凝った動画や長尺の映像では数ヶ月単位のスケジュールを見込む必要があります。
スケジュールには必ず余裕を持たせることが大切です。動画制作は各工程でのフィードバックや修正作業が発生するため、計画通りに進まない可能性も考慮しなくてはいけません。社内レビュー会議の日程がずれ込む、撮影日に予期せぬトラブルが起きる、といった想定外の遅れにも対応できるよう、当初の予定よりバッファを持ったスケジュールを組みましょう。「締め切りギリギリに依頼した結果、納期に間に合わない…」という事態を避けるためにも、計画段階でスケジュールに余裕を確保することが成功の第一歩です。
制作に必要なツール・リソースも確認しよう
動画制作には多くの要素が関わります。企画内容、撮影日数、使用機材、ロケ地、出演者(キャスティング)、衣装、ナレーション、音楽、動画の長さなど、挙げただけでも様々な要素があり、それぞれが制作費用やスケジュールに影響します 。クオリティを追求すると予算が青天井に膨らむ可能性もあるため、あらかじめ社内でどこまでリソースを投入できるか検討しておくことも重要です。
例えば、内製で動画を作る場合は撮影用のカメラや照明、録音マイク、撮影場所の手配、出演者の準備、そして編集用の高性能なパソコンと編集ソフト(Adobe Premiere ProやFinal Cut Proなど)といったツールが必要になります。アニメーション動画を自社で作るなら、IllustratorやAfter Effectsなどのデザイン・アニメ制作ソフト、それを扱える人材が必要でしょう。
制作会社に依頼する場合は、これら機材やソフト、人材は基本的に先方が用意しますが、自社のロゴデータや商品画像など提供すべき素材は事前に準備しておきます。また、社内から出演する人がいるならそのスケジューリング、社内で撮影するなら当日の会場手配など、社内リソースの調整も必要です。
以上が動画制作の基本的な流れと所要期間の目安です。続いて、実際に制作会社に依頼する前にやっておくべき準備について確認していきましょう。
動画制作会社・映像制作会社に依頼する前の準備
動画制作をスムーズに進めるには、依頼前の事前準備が欠かせません。特に初めて外部に動画制作を発注する場合、準備不足だと打ち合わせや制作工程で迷走してしまう恐れがあります。以下に、制作会社へ相談・依頼を行う前に社内で整えておきたい準備事項をまとめました。
- 目的・ターゲットの明確化
- 予算の策定
- 納期(希望納品日の設定)
- 必要な素材の準備と社内調整
それぞれ詳しく解説します。
目的・ターゲットを明確化し、伝えたいメッセージを固める
まず何より重要なのは、「誰に」「何を伝えたいのか」を明確にすることです。動画の目的やターゲットがあやふやなまま進めてしまうと、「誰に何を伝えたいのか分からない動画」になりかねません。マーケティング担当者として、以下の点を具体的に言語化しておきましょう。
- ターゲットの人物像:例)「30代後半・首都圏在住・製造業の経営者」のように、伝えたい相手の性別・年代、居住地、職業など
- 視聴後に与えたい印象や感情:例)安心感を持ってもらいたい、革新的な企業だと感じてほしい
- 視聴後に起こしてほしい行動:例)サービス資料の請求、問い合わせフォームからの連絡、ECサイトでの購入
これらをできるだけ細かく決定しておくことで、「いかにターゲットに刺さる動画にするか」が見えてきます。例えばターゲット設定では「20〜30代の女性」よりも「都市部在住でキャリアアップ志向の強い20代後半女性」とした方が、伝えるべきメッセージや適切な動画のテイストも絞り込みやすくなるでしょう。
同様に、動画の最終目的もはっきりさせます。「ブランド認知を広げたい」「新商品の特徴を分かりやすく伝えたい」「採用応募を増やしたい」等、何をもって動画の成功とするか社内で合意しておきましょう。目的が明確であれば、それに沿った内容(伝えるメッセージ)も自ずと定まります。逆に目的が曖昧だと、動画の方向性がブレてしまい効果が半減します。
予算と納期を設定する
次に予算と納期(目標とする完成時期)を決めておきます。予算によって動画のクオリティや尺、表現方法などできること・できないことが大きく左右されます。あらかじめ社内で上限予算を定めておけば、制作会社もその範囲で最適な企画を提案してくれます。「予算はいくらでも良いから最高のものを」と言われると企画も青天井になりますし、逆に「できるだけ安く」とだけ伝えてもクオリティが担保できなくなってしまいます。社内稟議などで確保できる予算感を早めに共有しましょう。
また、希望納期(いつまでに動画が必要か)も決めます。例えば「○月○日の展示会で上映したい」「△月の新商品リリースに合わせて公開したい」等の期限がありますよね。その場合、その日から逆算して十分間に合うスケジュールかを検討します。前述の通り制作には1〜3ヶ月程度かかるため、公開希望日の3〜4ヶ月前には制作会社に相談を始めるのが理想です。社内の決裁プロセスが長い企業では、契約書の締結に1ヶ月程度かかることもあります。契約手続きも含め、ゆとりを持った計画を立てましょう。
必要素材の整理と社内調整を行う
制作会社に渡す素材の準備も重要です。動画内で使用したい自社素材(映像・画像・音源など)があるかを確認し、ある場合は整理しておきます。自社で用意する素材が多ければ、その分費用を抑えられる可能性がありますし、逆に一から素材を制作会社に用意してもらうと費用増につながります。例えば「過去のイベント映像」「製品の写真」「会社のロゴデータ」「社内で撮影したインタビュー映像」など、使えそうな素材はピックアップしましょう。その際、**それらの素材を動画で利用して問題ないか(権利的に問題ないか)**も確認しておきます。社内で撮影・作成したものでも、写っている人の許可やBGMのライセンスなど注意すべき点はあります。制作会社にも素材を提供する際に伝えておくと安心です。
さらに、社内の関係者調整も忘れずに。動画制作にはマーケティング担当者だけでなく、場合によっては広報部門、営業部門、経営層などからの確認・承認が必要になります。**事前に関係各所に動画制作の目的や大まかな内容を共有し、協力を取り付けておきましょう。**撮影に自社社員が出演する場合は、その本人や所属部署の了承を得てスケジュールを確保しておく必要があります。社内ロケをするなら当日の会議室やオフィスの使用許可を取っておく、社外の撮影場所を使うなら総務や施設管理担当と調整しておく、といった具合です。
参考資料やイメージを用意する
最後に、制作会社との認識合わせをスムーズにするために参考資料を準備しておきましょう。もし**「こんなイメージの動画にしたい」**という参考映像があれば、事前に1〜3本ほどピックアップしておくことをおすすめします。例えば競合他社のプロモーション動画や、YouTubeで見つけたイメージに近い動画などです。初回の打ち合わせ時にそれらを見せながら説明することで、制作会社側も完成イメージを共有しやすくなり、企画提案や見積もりもより具体的になります。
また、社内ですでに映像のシナリオ案や絵コンテを描いてみるのも有効です。簡単な手描きでも構いません。企画の段階で考えているストーリーや演出プランがあれば資料化しておきましょう。これも立派なコミュニケーションツールになり、制作会社との打ち合わせがスムーズになります。自社の商品パンフレットや過去の広告コピーなど、伝えたい内容の参考になる資料もあれば併せて用意しておくと良いでしょう。
以上が依頼前にやっておくべき主な準備項目です。これらを万全にしておけば、いざ制作会社に問い合わせをした後のやり取りが格段にスムーズになります。次章では、実際にお問い合わせしてから契約に至るまでの流れと各工程のポイントを見ていきましょう。
お問い合わせから依頼までの流れ | 各工程のポイントも解説
ここからは、制作会社にコンタクトしてから正式に制作を依頼するまでの一般的な流れを解説します。具体的には、**「問い合わせ」→「ヒアリング(打ち合わせ)」→「企画提案・見積もり」→「契約」**というステップになります。それぞれの工程でのポイントも合わせて見ていきましょう。
1. お問い合わせ・ヒアリング
まずは気になる制作会社に問い合わせを行います。多くの場合、Webサイトの問い合わせフォームや電話から連絡を取り、簡単な相談内容を伝えて打ち合わせの日時を設定します。問い合わせ時には、「どんな種類の動画を作りたいか(例:商品紹介、会社紹介、採用動画など)」「納期の希望」「予算の目安」「公開媒体(Webサイト、YouTube、SNSなど)」といった基本情報を聞かれることが多いです。可能な範囲で答えられるよう、前章で準備した内容を伝えましょう。
次に初回ヒアリング(打ち合わせ)です。制作会社の担当者と対面またはオンラインでミーティングを行います。この場では、動画の目的やターゲット、伝えたいメッセージ、イメージなどを詳しく伝えます。ヒアリングではできるだけ具体的に要望を伝えることが大切です。抽象的に「かっこいい感じでお願いします」ではなく、「ターゲットは20代女性で、ブランドに親しみを感じてもらえるようポップな雰囲気にしたい」といった具合に、具体的な言葉で希望を述べましょう。また、「このポイントだけは絶対に伝えたい」という核となるメッセージは1つに絞ることも重要です。欲張って盛り込みすぎると焦点がぼやけてしまうため、「一番伝えたいことは何か?」を明確に伝達します。
初回ヒアリングでは他にも、「紹介したい製品やサービスは何か」「なぜその動画を作るのか(目的)」「想定する視聴者層」「検討している予算感」などが主に確認されます。これらはまさに事前準備で固めてきた項目なので、自信を持って回答しましょう。事前に社内で決めておいた内容(目的・ターゲット・予算など)は、この場でしっかり共有することが大切です。ヒアリングでの認識合わせが不十分だと、後々「イメージと違う…」という事態になりかねません。参考動画や資料もここで提示して、制作会社とのイメージをすり合わせます。
2. 企画提案・見積もり
ヒアリングで得た情報をもとに、制作会社はあなたの目的に沿った企画提案を行います。通常、後日改めて企画内容と見積もり金額をまとめた**「企画書・見積書」**が提示されます。企画書には以下のような情報が盛り込まれるのが一般的です。
- 動画の目的:何を達成したいか(例:サービス認知向上、採用応募増加など)
- 動画のコンセプトや方向性:どんな切り口・トーンで伝えるか
- 動画のおおまかな流れ・ストーリー:シナリオ概要や構成案
- イメージ画像やラフ画:主要シーンのラフスケッチや参考ビジュアル
- 想定される動画の長さ(尺)
- 制作スケジュール:各工程に要する期間と全体の納期予定
- 制作にかかる具体的な費用:内訳と合計見積もり金額
企画提案書と見積もりを受け取ったら、以下のポイントを必ず確認しましょう。
- ヒアリング内容と齟齬がないか:提案された方向性が、自社が伝えたいことから外れていないか。
- 不明瞭な部分はないか:専門用語や「一式」とだけ書かれた項目など、理解できない点は質問してクリアにします。
- 見積もり金額が予算を上回っている場合、調整は可能か:費用対効果を考え、優先度の低い要素を削るなどして予算内に収められないか相談します。
提案内容に問題がなく、費用面も納得できたら、企画および見積もり承認となります。この段階で「もう少し尺を短くして費用を下げたい」「ナレーションは入れずBGMのみにしたい」など、調整したいことがあれば伝えましょう。提案段階であれば柔軟にプランを練り直してもらえることがほとんどです。逆に契約後の大幅変更は難しくなるため、疑問や要望はこの時点で解消しておくのがベターです。
※もし複数の制作会社から提案を受けて比較する場合は、単純な金額だけでなく提案内容の質や得意分野、対応の丁寧さなども考慮しましょう。一番安い会社に決めたものの、「期待したクオリティと違った…」では本末転倒です。総合的に自社のニーズを満たしてくれそうな制作会社を選定してください。
3. 契約の締結
提案内容・見積金額に合意できたら、いよいよ契約締結となります。制作会社との間で業務委託契約書を交わし、正式に発注する流れです。契約書には、納品物の範囲や納期、支払い条件、著作権の取り扱い、機密保持などが明記されます。特に著作権や使用許諾範囲(完成動画をどこまで利用できるか)は確認しておきましょう。通常、完成した動画の著作権は制作会社に帰属し、発注企業はその動画を使用する権利を得る形が一般的ですが、自社で編集し直したり二次利用する予定がある場合は事前に取り決めておく必要があります。
契約書の内容に双方が合意し署名・捺印すれば契約成立です。契約が完了して初めて制作会社は正式にプロジェクト開始となります(会社によっては契約と同時に着手金の支払いが発生する場合もあります)。この契約までに思った以上に時間を要するケースもあります。特に大企業同士の契約では、契約書のレビューや決裁に1ヶ月程度かかる場合もあるとされています。社内の稟議や法務チェックなどを考慮し、契約手続きも逆算してスケジュールを組んでください。
契約が締結されたら、制作会社との間で具体的な制作工程(スケジュール)のすり合わせが行われ、実作業へと移っていきます。ここから先は実際の動画制作フェーズです。次章では、実写動画とアニメーション動画それぞれの場合に分けて、制作の流れと各工程のポイントを解説します。
【実写動画の場合】動画制作・映像制作の流れ
実写動画とは、カメラで人や物を撮影して作る映像コンテンツです。企業の紹介映像や商品PR動画、インタビュー動画、テレビCMなど幅広く活用されています。この章では、実写動画を制作する場合の主な工程とポイントを順を追って見ていきましょう。
工程は大きく**「企画・シナリオ作成」→「撮影」→「編集・仕上げ」**の3つに分かれます。それぞれ詳しく解説します。
企画・シナリオ作成
動画制作の土台となる企画設計とシナリオ(脚本)作成のフェーズです。前段のヒアリング内容をもとに、制作会社のディレクターやプランナーが具体的な企画を練り上げていきます。例えば、伝えるべきメッセージの優先順位を決め、全体のストーリー構成を考案します。社内で共有された要望があればここに反映されます。
シナリオ作成時には、必要に応じて絵コンテ(ストーリーボード)が作られます。絵コンテとはシナリオの各シーンを簡単なイラストで描いたもので、完成映像のイメージを視覚的に共有するためのものです。セリフやナレーションに対応してどんな映像が流れるかをコマ割りで示した設計図のような役割を果たします。絵が苦手な場合は、写真や過去動画をコラージュしたビデオコンテと呼ばれる簡易動画が用いられることもあります。いずれにせよ、この段階でクライアント(発注側)にも絵コンテが共有されるのが一般的です。
マーケ担当者としては、提案されたシナリオや絵コンテの内容をしっかり確認しましょう。ストーリー展開や台詞回し、演出イメージに違和感がないかチェックします。この段階での認識ズレは後工程の大幅な手戻りにつながるため、気になる点は遠慮せず質問・修正依頼を行い、納得のいくまでブラッシュアップします。例えば「このシーンの表現は当社のブランドイメージと少しズレているのでは?」など感じたことは率直に伝えましょう。企画・シナリオ段階でしっかり擦り合わせを行うことで、後の撮影・編集がスムーズに進み、完成度の高い動画に近づきます。
撮影の進め方(機材・ロケ地・キャスティング)
シナリオと絵コンテが固まったら、いよいよ撮影準備に入ります。まずは撮影スケジュールの策定です。撮影日程を決め、当日のタイムテーブル(香盤表)を作成します。撮影に必要な機材の手配も重要です。カメラやレンズ、照明機材、マイクなど、シーンに応じて適切なものを準備します。ドローン撮影やクレーン撮影が必要なら専門オペレーターの手配も必要です。
次にロケ地の選定です。シナリオに沿って撮影場所を決めます。自社オフィスや工場内で撮る場合は事前に社内許可を取得し、撮影クルーが入れるよう段取りします。外部のロケ地を使う場合、下見(ロケハン)を行って撮影条件を確認し、必要なら使用許可や撮影許可を申請します。屋外撮影では天候リスクも考え、予備日を設けたり雨天時プランを用意しておくこともあります。
そしてキャスティングです。映像に登場する人物を誰にするか決めます。自社の社員や経営者が出演するケースもありますし、プロの役者やモデル、ナレーターに依頼する場合もあります。ターゲット層に訴求力のある人物像を選びましょう。出演者を外部から起用する際は、制作会社がオーディションやキャスティングを代行してくれます。候補者のプロフィールや過去実績を共有してもらい、イメージに合う人を選定します。
撮影当日に向けて衣装や小道具の準備も行います。出演者の衣装は自前か用意するか決め、ブランドイメージに合った装いになるよう注意します。製品のデモ映像なら製品本体や付属品を用意し、必要なら予備も準備します。撮影現場で「あれが足りない!」とならないよう、リストアップして持ち込みましょう。
撮影当日は、ディレクターの指示のもとカメラクルーや音声スタッフが動きます。マーケ担当者も可能であれば立ち会い、現場で内容を確認することをおすすめします。現場にいることで、その場での軽微な演出変更や社内チェックを迅速に行えますし、万一シナリオと異なる進行になりそうな場合に気付けます。とはいえ基本はプロに任せ、予定していたカットがすべて撮れるよう協力しましょう。
撮影では1シーンに対し複数回テイクを撮るのが通常です。後の編集でベストなカットを選ぶためですが、逆に言えば撮り逃し厳禁です。一連の撮影が終わったら、ディレクターと一緒に必要な映像がすべて収録できているか確認します。もし不安があればその場で追加撮影することも可能なので、現場で解決しておきます。撮影日程が複数日ある場合は、日程間で撮り漏れがないよう共有しましょう。
なお、撮影日数は可能な限り少なく抑えることもポイントです。撮影日が1日増えるごとに人件費や機材レンタル費が増加するため、予算に直結します。一般に撮影費用の相場は1日で約30万円、2日だと約50万円と言われます。撮影を1日以内に終えられれば見積額を約20万円抑えられる計算です。もちろん内容によって必要日数は変わりますが、段取り良く効率的に撮影することがコスト管理にも繋がる点を覚えておきましょう。
編集・仕上げ(テロップ・BGM・ナレーション)
撮影が完了すると、次は編集作業に入ります。撮影した映像素材をもとに、編集担当者が動画の形に組み上げていきます。編集では、シナリオに沿ってベストなテイクを選び、シーンをつなぎ合わせていきます。必要に応じてテロップ(字幕スーパー)やタイトル、グラフィック要素も追加されます。例えば強調したいキーワードを画面に大きく表示したり、説明を補足する字幕を入れたりといった具合です。場合によってはイメージイラストやアニメーション効果もここで挿入されます。編集担当者は、完成台本のイメージに沿うよう映像を構成し、視聴者に伝わりやすいテンポや演出を追求します。
映像面の編集が進むと並行して音響面の仕上げ(MA作業)も行われます。MAとは「マルチオーディオ」の略で、映像に音声をなじませて完成させる作業を指します。具体的には、編集済みの動画にナレーション音声やBGM、効果音を加えていく工程です。ナレーション担当の声優・アナウンサーによるナレーション収録もこの段階で行われます(事前に収録済みの場合もあります)。収録スタジオでプロのナレーターが台本に沿って読み上げ、それを映像に合わせて配置します。BGM(バックグラウンドミュージック)は動画の雰囲気に合った楽曲を選定し、必要に応じて購入・ライセンス手続きを行って使用します。効果音も場面に応じて挿入し、映像の臨場感を高めます。
音声を含めた編集が一通り完了すると、制作会社からプレビュー用の仮完成動画データが送られてきます。この段階でクライアント側で試写チェックを行います。出来上がった映像を社内関係者と確認し、意図した内容になっているか、修正すべき点はないかを洗い出します。テロップの表記ミスや色味の調整、ナレーションと映像のタイミングなど、細部までチェックしましょう。万一修正してほしい箇所が見つかった場合は、具体的に指示を出して再度修正を依頼します。例えば「〇分〇秒のテロップの文言を〇〇に変更してください」「最後のロゴ表示をもう1秒長くしてください」といった具合です。
修正リクエストを反映し最終調整が完了したら、納品となります。納品形態は契約時に定めたとおりです。一般的にはMP4など指定フォーマットのデータがオンラインで納品されます。テレビ放映用であれば放送局の指定フォーマットで出力し、必要に応じてテープやハードディスクで納品することもあります。納品ファイルを受け取ったら、再生確認を行い問題ないことを確認しましょう。
以上が実写動画制作の一連の流れです。企画段階から納品まで、各フェーズで綿密なコミュニケーションを取りながら進めることで、納得のいく映像が完成します。それでは次に、アニメーション動画の場合の制作フローを見ていきます。
【アニメーション動画の場合】動画制作・映像制作の流れ
アニメーション動画とは、イラストや図形などの静止画素材に動きを付けて映像化する手法です。モーショングラフィックスやキャラクターアニメーション、ホワイトボードアニメーションなど様々なスタイルがありますが、いずれもカメラ撮影を行わない点で実写と異なります。ここでは、アニメーション動画を制作する場合の工程とポイントを解説します。
基本的な工程は実写と同様に**「企画・シナリオ」→「制作」→「編集・仕上げ」**ですが、その中身が少し異なります。
ストーリーボード作成(構成案の可視化)
アニメーション制作では、ストーリーボード(絵コンテ)作成が特に重要です。実写以上に、最初の段階で完成イメージを共有しておかないと、後から軌道修正するのが難しいためです。絵コンテにはシーンごとに簡単なスケッチと説明文が描かれ、どのタイミングでどんなアニメーションが起きるか示されています。これは台本にラフな絵を加えて分かりやすくした資料で、制作会社内だけでなく発注企業にも共有されるのが一般的です。
シナリオ(台本)自体は実写の場合と同様に文章で作成しますが、アニメーションの場合はそれを基に具体的なビジュアルプランを立てる必要があります。キャラクターが登場するならデザインイメージ、アイコンや図解で見せるならそのスタイル、といった具合に、文章では伝わりにくい部分を絵コンテ上で補足します。
発注側のマーケ担当者は、この絵コンテを受け取ったら細部まで目を通し、内容を正確に理解する必要があります。もしこの段階で認識の相違があると、後で大きな手戻りが生じかねません。例えば「このキャラクターはもう少し若々しい印象にしたい」「製品画像はリアルな写真ではなくイラスト風にしたい」といった要望があれば、絵コンテ段階で制作側にフィードバックします。疑問点は遠慮なく質問し、納得いくまで何度でも修正を繰り返して、完成形のイメージをすり合わせましょう。
なお、最近では絵コンテの代わりに**「ビデオコンテ」**と呼ばれる簡易動画を用いる場合もあります。例えば静止画をスライドショー状につなぎナレーションの仮音声を当てた動画で、より動きを感じられるコンテです。手法はどうあれ、完成イメージの共有がこの段階のゴールです。
アニメーション制作のプロセス
絵コンテ(ストーリーボード)が確定したら、本格的なアニメーション制作作業に入ります。まずは素材の制作です。デザイナーが絵コンテをもとに必要なイラスト素材やグラフィックを描き起こします。登場キャラクターのイラスト、背景のデザイン、アイコンや図表パーツなど、動かす要素をすべて準備します。既存のブランドキャラクターやロゴなどを使う場合も、動画用に最適化(高解像度化やパーツ分解など)します。
素材が揃ったら、いよいよ**アニメーション(動画化)**の工程です。アニメーターが専用ソフトを使って素材に命を吹き込みます。例えば、キャラクターが歩くシーンなら手足をパラパラマンガの要領で動かすキーフレームを設定します。グラフが伸びていくシーンなら棒グラフの描画を徐々に表示させるキーフレームを打つ、といった具合です。昨今はAfter Effectsのようなツールでモーションを付けることが多いですが、手描きのコマ撮りアニメーションの場合は各フレームをイラストレーターが描いて繋げることもあります。
アニメーション制作には一定の時間がかかりますが、この間にナレーション原稿のブラッシュアップや仮ナレーションの収録を進めることもあります。実写と異なり撮影がない分、ナレーションのタイミングが映像の尺を決めることが多いため、ナレーション原稿(台本)の分量と動画長さのバランス確認は重要です。必要であればこの時点で仮のナレーション音声を録り、映像制作側がタイミングを合わせやすいようにすることもあります。
制作会社によっては、途中段階でアニメーションの進捗映像を共有してくれる場合もあります。例えば一部シーンだけ動かしたラフ動画を見せて、「このキャラクターの動き方でイメージ合っていますか?」と確認を取ることもあります。全体は難しくても要所要所ですり合わせをしてもらえると安心ですね。
ナレーションやBGMの挿入
アニメーションパートの制作が完了したら、仕上げとして音声要素の挿入と調整を行います。基本的な流れは実写動画の編集工程と似ています。まず、プロのナレーターによる本番ナレーション収録を行います。スタジオで台本全文を録音し、それをアニメーション映像とシンクロさせます。次に、動画にふさわしい**BGM(音楽)**を決定し挿入します。明るい動画ならアップテンポの曲、真面目な内容なら落ち着いた曲など、シーンに合わせて選曲します。必要に応じて効果音も足し、例えばアイコンがポップアップするシーンで「ポン!」という音を入れるなど演出を強化します。
こうした音入れ・音調整の工程は、実写同様MA作業と呼ばれます。ナレーション音声とBGM・効果音との音量バランスを取り、聞き取りやすく臨場感のある音に仕上げます。高品質な動画では専用のMAスタジオで行うケースもありますが、通常の企業向け動画であれば編集と同じ作業環境で行われることが多いです。
映像と音がすべて合わさったら、クライアントに完成前のプレビュー版が共有されます。ここで再度、内容チェックです。アニメーションが意図通りの動きになっているか、ナレーションのトーンや読み間違いはないか、色使いやデザインに不備はないか等、細かく確認します。例えば「テロップのフォントが自社ガイドラインと違う」「グラフの数値が最新版に更新されていない」など、気付いた点はリストアップして修正を依頼します。修正依頼の流れも実写動画と同じです。
最終修正が反映され問題が無ければ納品となります。納品形式も実写と同様にデータで受け取るのが一般的です。こうしてアニメーション動画が完成します。
実写動画と比べたアニメーション動画制作のポイントをまとめると、前半の設計(絵コンテ)に時間をかけ、完成イメージを固めることが成功のカギです。撮影こそ無いものの、イラスト作成やモーション制作に工数がかかるため、大幅な方向転換は容易ではありません。その分、細かな修正(色変更やテロップ文言変更など)は実写より対応しやすいメリットもあります。いずれにせよ、発注側としてはコミュニケーションを密にとり、認識齟齬を最小限にしていく姿勢が大切です。
以上、アニメーション動画制作の流れを見てきました。それでは最後に、動画制作を成功させるためのポイントや注意点を整理し、本記事のまとめとします。
動画制作・映像制作を成功させるためのポイントや注意点
ここまで動画制作の具体的な工程を解説してきましたが、プロジェクトを成功させるためにはいくつか共通する重要ポイントがあります。最後に、特に押さえておきたいポイントや注意点を3つ取り上げます。
スケジュール管理のコツ — 余裕を持った計画が鍵
動画制作ではスケジュール管理が極めて重要です。関係者も多く工程も複雑なため、計画通りに進むとは限りません。納期から逆算して無理のない計画を立て、さらにバッファ期間を設けるくらいが丁度良いです。例えば完成希望日の1〜2週間前には映像を完成させて社内チェックを終えられるようにするなど、「予定の予定」を作っておきます。
また、各マイルストーン(シナリオ確定、撮影日、試写日など)に対して社内承認者のスケジュールも確保しておきましょう。決裁者の不在でレビュー会議が延期…とならないよう、あらかじめスケジュールを周知しておくことが肝心です。
フィードバックは迅速に行うこともポイントです。修正依頼が遅れるとその分完成も遅れます。社内調整に時間がかかりそうな場合は、制作会社にその旨伝えつつ並行作業できることはないか相談しましょう。
万一スケジュールが逼迫してきた場合でも、焦ってクオリティを落としては本末転倒です。間に合わないと思ったら早めに制作会社に相談し、工程を省略できないか、納期を調整できないか打ち手を検討します。最悪公開日をずらす決断も必要になるかもしれませんが、重要なのは事前にリスクを共有して対応策を講じることです。
コストを抑える方法 — 効率化と社内資産の活用
高品質な動画を作ろうとするとコストも膨らみがちです。限られた予算内で最大の効果を出すには、費用対効果を意識した工夫が必要です。
①撮影や制作の効率化:先述の通り、撮影日数を減らすことは大きなコスト削減につながります。綿密な香盤表を用意し無駄のない撮影進行を心がけましょう。また、撮影場所をまとめたり、同じ日に複数パターンの映像を撮って使い回すことも一案です。例えばインタビュー動画を撮影するなら、ついでに社内風景の汎用映像も撮ってストックしておくなど、一石二鳥を狙います。
②自社素材の活用:社内に使える素材があれば可能な限り活用しましょう。自社で用意できる動画・静止画素材があるかを確認し、活用できるものは提供するのがおすすめです。例えば「以前イベントで撮影した映像がある」「製品の写真は豊富に持っている」などの場合、新規に撮影・制作する手間を省けます。ただし画質や解像度が低いものは使えないこともあるので、その点は制作会社と相談してください。
③優先度の見極め:全てを完璧に盛り込もうとするとコストオーバーになります。限られた予算で最大効果を出すには、「これは譲れない」というポイントと「妥協できる部分」を仕分けすることが重要です。例えば、ナレーションはプロを起用するが出演モデルは社内スタッフで代替するとか、アニメーションの作り込みは最小限にしてその代わり尺を長めに確保する、といったトレードオフを検討します。予算内で可能な選択肢を制作会社に提案してもらうのも良いでしょう。経験豊富な制作会社なら、「この予算規模ならここにお金をかけ、ここは簡略化しましょう」といったアドバイスをくれるはずです。
④複数社への相見積もり:制作費用の相場感を知るために、複数の制作会社から見積もりを取るのも一つの手です。ただし単純に一番安い会社を選ぶのではなく、提案内容と実績を見比べて判断してください。安くても仕上がりが悪ければ意味がありません。費用交渉する際も、「他社は〇〇万円だったので下げてほしい」という伝え方より、「〇〇万円だと助かるがクオリティは担保したい」と率直に相談する方が建設的です。
最後に、制作会社に予算上限を正直に伝えることも大切です。言いにくいかもしれませんが、はじめに伝えておくことで、その範囲内で最大限のプランを考えてくれます。隠していても結局出てきてしまうものですから、オープンに話してしまいましょう。
外注 vs 内製の判断基準 — プロの力を上手に活用する
動画制作を**「外注するか」「内製(社内制作)するか」は悩みどころです。昨今の傾向では、一部の企業は内製チームを持ちSNS向け動画を量産していますが、外部の制作会社に委託するケースも増えています。2024年の調査では、完全に社内だけで動画制作する企業は38%と前年より減少し、外部委託する企業は24%(前年の11%から大幅増)に増えています。残りの38%は内製と外注を組み合わせており、これも前年から増加しています。このように多くの企業が内製と外注を併用するハイブリッド戦略**を取っているのが現状です。需要の増加に応じてプロの力を借りることが一般的になってきていると言えるでしょう。
では具体的にどう判断するか。ポイントは社内リソースと求めるクオリティです。
- 内製が向いているケース:社内に動画編集スキルを持つ人材や撮影機材が既にあり、比較的簡易な動画をスピーディーに量産したい場合です。例えばSNSに載せる短いハウツー動画を毎週作る、といった場合は内製チームがあると便利です。細かな修正も自前で効くので融通が利きます。また、予算が極めて限られている場合も内製せざるを得ないでしょう。ただし、社内スタッフの労力コストや機材購入費なども考慮に入れて決める必要があります。
- 外注が向いているケース:クオリティが重要な動画(ブランドイメージ映像やTV CMなど)や、高度な技術や発想が必要な動画はプロに任せる方が安心です。プロの制作会社は豊富な知見とクリエイティビティを持っており、社内では思いつかないような表現で魅力的な動画に仕上げてくれる可能性があります。また、大規模プロジェクトで多数のスタッフが必要な場合や、社内に余力が無い場合も外注が適しています。外注すれば自社スタッフはコア業務に集中できますし、納品スケジュールも契約で担保されます。
- ハイブリッド(内製+外注):内製と外注を組み合わせるのも賢い戦略です。例えば日常的な短尺動画は内製し、キャンペーン用のメイン動画は外注する。あるいは企画や素材制作は内製し、編集や仕上げだけ外注する、といったパターンもあります。実際、多くの企業が自社で対応可能な部分は担いつつ、足りない部分だけ外部委託しています。外注部分を明確にすることでコスト管理もしやすくなります。
いずれにせよ、初めて動画制作に取り組む場合は、まずは信頼できるプロに依頼することをおすすめします。プロと協業する中でノウハウを社内に蓄積し、徐々に内製できる範囲を広げていくのが理想です。その際、自社のブランドや製品知識は社内にしかない強みなので、それを積極的に外部パートナーに共有し、コラボレーションして良い作品を作りましょう。外注する場合でも、ブランドガイドラインや過去のクリエイティブ事例を共有しておくと、仕上がりに一貫性が出ます。
最後に、外注先を選ぶ際のポイントとしては、実績や得意分野、こちらの業界に対する理解度、レスポンスの速さなどが挙げられます。提案内容ややり取りを通じて「この会社なら信頼して任せられる」と思えるパートナーを見つけましょう。
【まとめ】動画制作は、スケジュールに余裕を持って依頼しましょう
本記事では「動画制作の流れ」を企画から納品まで解説し、各段階でのポイントを紹介しました。最後に重要なポイントを振り返ります。
まず、動画制作は時間がかかるものです。1〜3ヶ月程度は見込んで、早め早めの行動を心がけましょう。特に初めての場合、想定外の手間や調整ごとが発生しがちです。「納期に余裕を持つ」ことが最大のリスクヘッジになります。
次に、目的・ターゲットの明確化がすべての出発点です。ここが曖昧だと最後までブレた動画になってしまいます。「誰に何を伝えたいか」「動画でどんな成果を得たいか」を社内でしっかり擦り合わせてから臨みましょう。ターゲット設定が不十分なことは失敗の典型例です。
また、欲張りすぎないことも大切です。あれもこれもと情報を詰め込みすぎると、結局何が言いたいのか分からない動画になります。伝えたいメッセージは一点に絞り、その他は潔く捨てる勇気も必要です(追加情報はWebページや資料で補完するなど工夫しましょう)。
社内の協力体制も成功の鍵です。関係部署には早めに根回しをし、素材提供やレビューに協力してもらえるよう段取りしてください。動画制作はチーム戦ですので、部署を超えた連携が求められます。
最後にチェックリストを用意しました。動画制作プロジェクトを進める際には、以下の項目が満たされているか確認してみてください。
- 目的・ターゲットが明確か?(誰に何を伝える動画か定義済み)
- 主要メッセージは何か?(欲張らず一点に絞れている)
- 予算と納期の社内承認は得たか?(上限額と締め切りを設定)
- 社内の必要な素材は揃えたか?(ロゴ・写真・過去動画など)
- 参考になる他社動画やイメージ資料を用意したか?
- 信頼できる制作パートナーを選定したか?(実績・対応を確認)
- 各工程で関与すべき社内メンバーに共有したか?(事前にスケジュールも連絡)
- スケジュールに十分な余裕があるか?(想定外の事態に備えたバッファ含む)
- 完成動画の社内チェック体制は万全か?(関係者全員で最終確認)
- 著作権や使用許諾の問題はないか?(音楽や素材のライセンス確認)
これらをクリアしていれば、きっと動画制作は成功するでしょう。万全の準備のもと、プロジェクトを進めてみてください。
初めての動画制作は不安も多いかもしれませんが、ポイントを押さえて進めれば決して難しいものではありません。社内外の力をうまく借りながら、ぜひ成果の出る動画コンテンツを完成させてください。
動画制作ならサンキャク
「とはいえ、自社だけで進めるのは不安だ」「信頼できるパートナーに任せたい」という方も多いでしょう。そのような場合は、ぜひサンキャク株式会社にご相談ください。サンキャク株式会社は、動画制作とSNSマーケティングを融合させたサービスを提供する制作会社です。単に動画を作るだけでなく、お客様のターゲット層に合わせて最適なSNSプラットフォームを選定し、効果的な動画コンテンツの制作・配信まで行えるのが強みです。
特にSNSマーケティングに関する豊富なノウハウと実績を有しており、動画制作からSNS運用、さらには広告配信まで一貫したサービスで企業の情報発信をサポートしています。実際に、大手企業のYouTubeチャンネル運用やビジネスメディアの動画企画なども手掛けており、データに基づく企画力と分析力には定評があります (サンキャク株式会社の制作情報 | 神奈川県の動画制作会社 | 動画幹事)。BtoB企業の動画マーケティング支援にも強みを持っており、自社の商品・サービスの魅力を最大限に引き出す動画戦略を提案いたします。
サンキャクでは、企画段階から丁寧にヒアリングを行い、目的達成に最適な動画プランをご提案します (サービス – 動画制作 | 動画制作・映像制作ならサンキャク | 大手の実績豊富、成果を出す動画制作会社 )。企業ブランディング映像、商品PR動画、採用動画、SNS向け短編動画など幅広いジャンルに対応可能です。撮影が必要な実写動画から、分かりやすく伝えられるアニメーション動画まで、経験豊富なクリエイティブチームが在籍しております。
実績の一部は公式サイトの制作事例ページでもご覧いただけます。例えば、「グッドパッチ」様のイベントプロモーション映像や、大手IT企業「DeNA」様のYouTube企画運営など、多くのプロジェクトで成果を上げてきました。
お問い合わせから制作開始までの流れもスムーズです。お問い合わせ後、当社プロデューサーがヒアリングを実施し、数日以内に企画提案・お見積もりをご提示します。ご納得いただいてから契約・着手となりますので、まずは相談だけでも大歓迎です。
「どのような動画にすれば良いかイメージが湧いていない」という段階でも大丈夫です。マーケティングの課題やターゲット層を伺いながら、一緒に企画を練らせていただきます。動画活用の初心者の方にも丁寧にご説明し、ご安心いただけるよう進行いたします。
動画制作のご相談やお見積もり依頼は無料ですので、ぜひお気軽にお声がけください。お問い合わせはいつでも可能です。専門スタッフが貴社の課題をヒアリングし、最適な動画活用プランをご提案いたします。
貴社のマーケティングにおいて、動画という強力な武器を最大限に活用しましょう。動画制作ならサンキャク株式会社にお任せください。お問い合せ、お待ちしています!







